皆さんは「てんかん」と「ひきつけ」の違いを知っていますか?
皆さんは「てんかん」と「ひきつけ」の違いを知っていますか?
なんとなく使っている言葉ですが、救急車を呼ぶ際に間違えると、対処法が違ってきます。
今回は、「てんかん」と「ひきつけ」の違いと原因と症状、さらに対処法まで解説します!
目次
はじめに|「てんかん」と「ひきつけ」はどう違うのか?
「けいれん」と聞くと、体がガクガク動いたり、意識が消えたりするイメージがあるかもしれません。
でも、けいれんには「てんかん」と「ひきつけ(熱性けいれん)」という2つの種類があり、
それぞれの原因や対処法が違います。
この違いを知っておいて、もし身近な人が発作を起こしたときは、落ち着いて行動できます。
「てんかん」と「ひきつけ」の違いを比較
最初に「てんかん」と「ひきつけ」の特徴を見ていきましょう!
てんかんとは?
てんかんとは脳にある神経細胞が過剰に興奮をしてしまい、発作を繰り返してしまう脳の病気です。
てんかん発作と間違われやすい病気がいくつかあります。
失神・心因性発作・過呼吸・パニック発作・脳卒中・中毒症状など。
この他にも様々な病気と間違われることがあります。
ひきつけとは?
自分の意志とは関係が全くなく、手足が突っ張ったり硬直したりします。
「ひきつけ」というのは「痙攣」を指す言葉だそうです。
また、小児痙攣の時に使われる言葉だそうです。
熱が出たときに起こりやすいのが、熱性痙攣であり特徴です。
2つの違いを表で比較(原因・症状・発症年齢・持続時間など)
| 項目 | てんかん | ひきつけ(痙攣) |
| 原因 | 脳の電気の乱れ | 高熱が原因 |
| タイミング | いつでも | 熱が出始めたときなど |
| 回数 | 頻繁 | ほぼ1回 |
| 発熱 | なし | ある場合・38度以上 |
【原因】「てんかん」と「ひきつけ(痙攣)」が起こる理由とは?
てんかんの主な原因(脳の異常・遺伝・外傷など)
突然意識を失って反応がなくなるなど「発作」を繰り返します。
原因や症状は人によって違います。
乳幼児から高齢者まで、どの年齢層でも発病する可能性があります。
てんかんは、脳の中の電気の流れがうまくいかないことで発作が起こります。
原因はいろいろありますが、次のようなものがあります。
- 生まれつきの体質(親や家族にてんかん人がいる場合、なりやすいことも)
- 決断に強い事がある(事故や転倒など)
- 病気が原因(脳の病気や感染症の脳炎・髄膜炎など)
てんかんの中でも、「良性てんかん・難治性てんかん」があります。
難治性てんかんは「ドラベ症候群」といって、多くの場合1歳までに全身、半身の痙攣で発症し、
その後も痙攣を何度も繰り返す病気があります。
ひきつけ(熱性痙攣)の主な原因(発熱・感染症・体質など)
ひきつけ(熱性痙攣)は主に、発熱時に起こります。
主な原因やメカニズムはいまだわかっていないそうです。
ひきつけ(熱性痙攣)の具体的な特長や対処法をまとめた記事があるので、
詳しくはこちらから読んでみてください。
【症状】発作時の違いと見分け方
てんかんの症状と発作の特徴(部分発作・全体発作)
てんかんの大きな特徴として、「いつ・どこで起こるのかわからない」ということです。
てんかん発作が起これば、1週間の間に何度も発作が起こる場合もあれば、2年間間が空くということもあります。
てんかんの症状がどのような物なのか、下記にまとめてみました。
~主な症状~
・焦点発作
体の一部がぴくぴく
・全般発作
ぼーっとして意識がはっきりしていない
・自動症発作(意識減損焦点性発作)
歩き回る、顔をなでる、口を動かす
・失神状態
急にコミュニケーションがとれない
症状は人それぞれです。
体の一部がぴくぴくしたり、ぼーっとしたりすることだけが発作ではありません。
自覚ができないので、周囲の人からの助けが必要です。
ひきつけの症状(熱性痙攣など)
ひきつけ(熱性痙攣)は小学校就学前に起こりやすいです。
また良性の痙攣と悪性の痙攣があります。
ひきつけ(熱性痙攣)の具体的な特長や対処法をまとめた記事があるので、
詳しくはこちらから読んでみてください。
【対処法】てんかん・ひきつけ(熱性痙攣)の対処法
てんかん・ひきつけ(熱性痙攣)が起きた時の対処法
てんかん・ひきつけ(熱性痙攣)には適切な対処法があります。
また、どちらも対処法は同じなので、どんなものか見ていきましょう。
以下にまとめてみました。
また詳しく詳細を知りたい方は、こちらから読んでみてください。
~4つの対処法~
1.安全確認&慌てない
周囲の安全確認をし、二次被害が無いようにしましょう。
冷静に対処するために、まずは落ち着きましょう。
2.時間管理
てんかん・ひきつけ(熱性痙攣)の時間管理は必要です。
繰り返すのか・長時間なのかで、緊急度が変わってきます。
3.回復体位
回復体位をとることで、嘔吐物が口から流れやすくなります。
4.動画やメモを取る
動画やメモを取ることで、救急隊員や医師の役に立ちます。
どんな病状なのか・どのぐらい深刻なのか判断ができます。
【まとめ】正しい知識で正しく対処しよう
適切な対処で後遺症を防ぐことがでたり、軽くなったりします。
慌ててしまう気持ちもわかります。
まずは的確な判断をするために、冷静になりましょう。
また、知識として覚えておくことだけでも、周りを助けることができます。
覚えておくことで損することはないので、是非時間があるときに勉強しましょう!
その他にも記事を更新中!トップページのこちらから読んで行ってください!
世界中のすくすく育つ子供たちに乾杯!
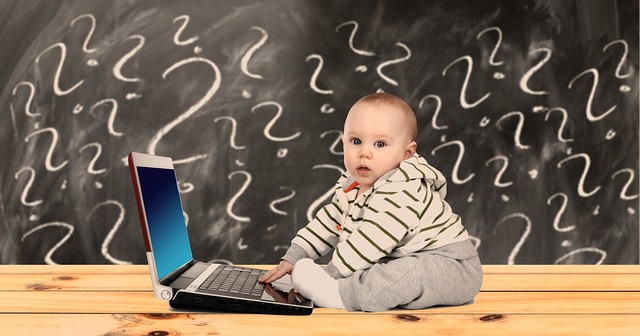


コメント